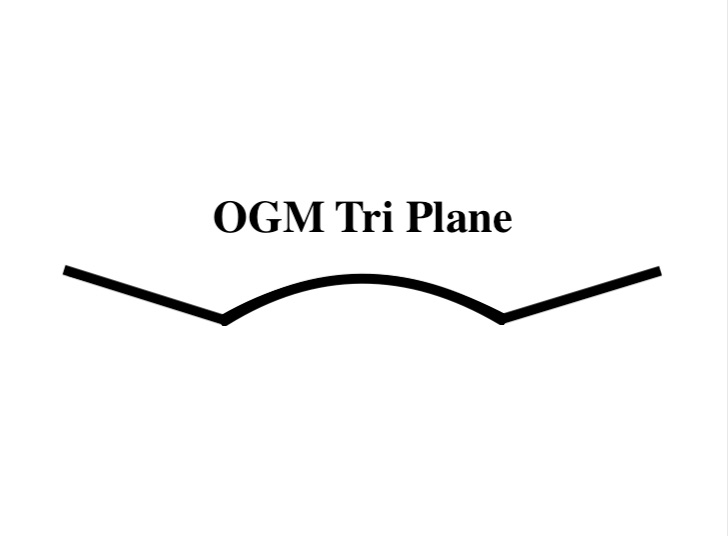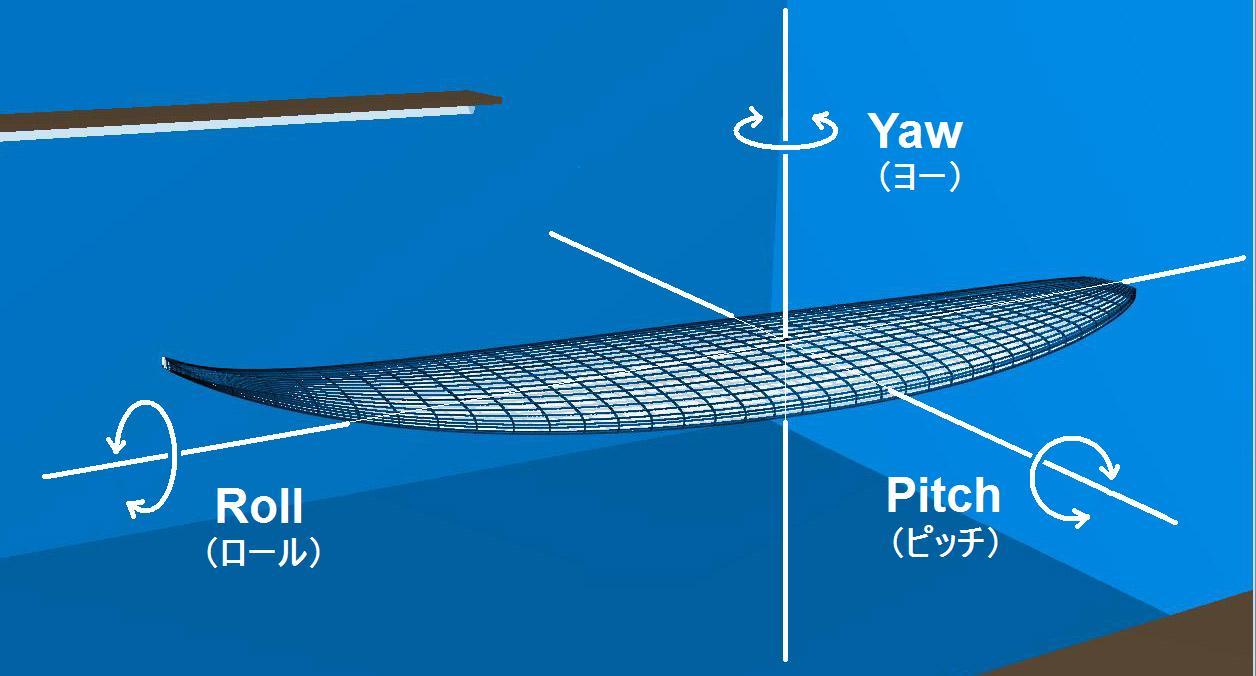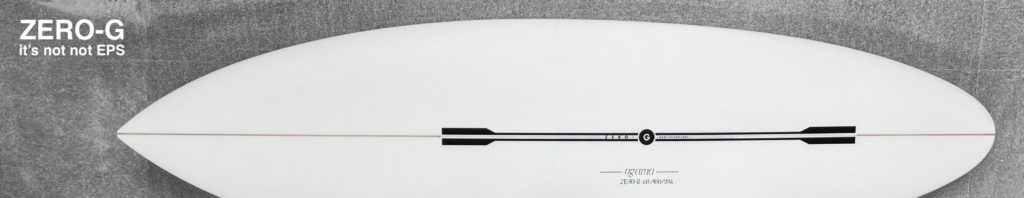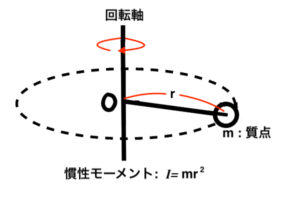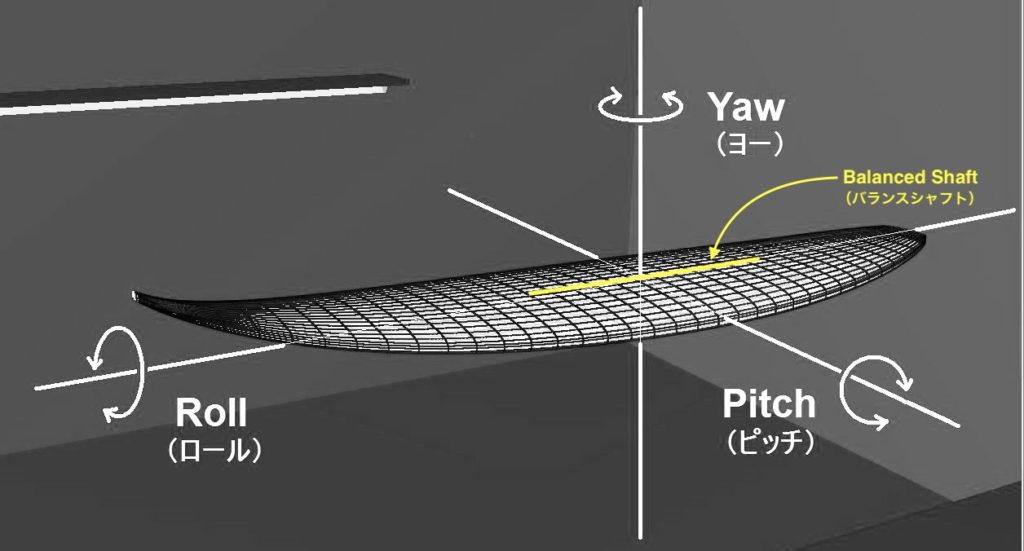サーフィンは難しいスポーツです。
サーファーは、誰もが上手くなりたいと思っていますが、なかなか上達できません。
そもそも上手くなるためには、まず、波に波に乗らなくては始まりませんが、この一番最初に来るテイクオフがそもそも簡単ではありません。
一生懸命パドルしてるのだけど、なかなかボードが滑り出さず、やっとテイクオフできたと思ったら、その瞬間に、波が底掘れしてパーリングなんてこと、よくありますよね。
また、待っていた波が自分の前にやってきても、突然他のサーファーが横から現れて簡単に波を奪ってしまうこともあります。
それに加えて、体力の衰えや気力の低下、体重の増加など、挙げればきりがありません。
本当にサーフィンは難しいスポーツですね。
サーフボードで解決できるかもしれません。
私は、これらの困難な問題のほとんどが、自分に適した適切なサーフボードを手に入れることで解決できると考えています。
ボードが小さすぎると、パドリングの速度が遅くなり、波をキャッチすることができません。
逆に、ボードが大きすぎると、操作性が悪く、水中で機敏に動くことができず、波に対する正確なアプローチができません。
確実に乗ることができる自分に合ったボードを持つことで、あなたのサーフィンは確実に進歩するでしょう。
サーフボードにはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や選ぶ基準は無数に存在します。
氾濫する情報の中で、サーファーが本当に自分に合ったボードを手に入れるのはなかなか難しいことです。
見た目がほとんど同じように見えるサーフボード も、わずかな違いでその特性が大きく変わります。
一方のボードは簡単に乗れるのに、他方のボードはテイクオフすらできないということが本当に起こるのです。
自分にぴったり合ったサーフボードを手に入れる。
自分にぴったり合ったサーフィンボードを手に入れるために、OGMは2010年にShapeShopをオープンしました。OGMでは、多くのプロ選手用のサーフボードをシェイプしていますが、同じ手順でオーダーを受け付けます。
あなたのライディングスタイル、レベル、使用する波のサイズやコンディション、目指しているサーフィンのスタイルなど、さまざまな情報と要求を話し合い、最適なサーフボードを決定します。
プロ選手たちは目的のサーフボードを手に入れるために、妥協することなく努力します。
自分に合わないボードを無理に乗り続けることは、将来においてもったいないと思いませんか?
海で他のサーファーよりも速く、簡単にテイクオフし、スムーズなライディングができることは楽しいと思いませんか?
自分にぴったりのボードと出会うことで、あなたのサーフィン人生は大きく変わるでしょう。
自分に最適なボードを知るために、今すぐ行動しましょう。
自分に合ったサーフボードを手に入れることを早く実現させてください。
サーフィンは、一生のスポーツです。
私は、それが単なるスポーツではなく、むしろ生き方そのものや人生そのものだと考えています。
OGM ShapeShopで、自分のサーフスタイルやライフスタイルに最適なサーフボードを手に入れてください。
サーフボードは扱いやすいものであるべきです。
あなたのために特別につくられたものであるべきです。
そして、楽しいものであるべきです。
私は喜んであなたのお手伝いをします。