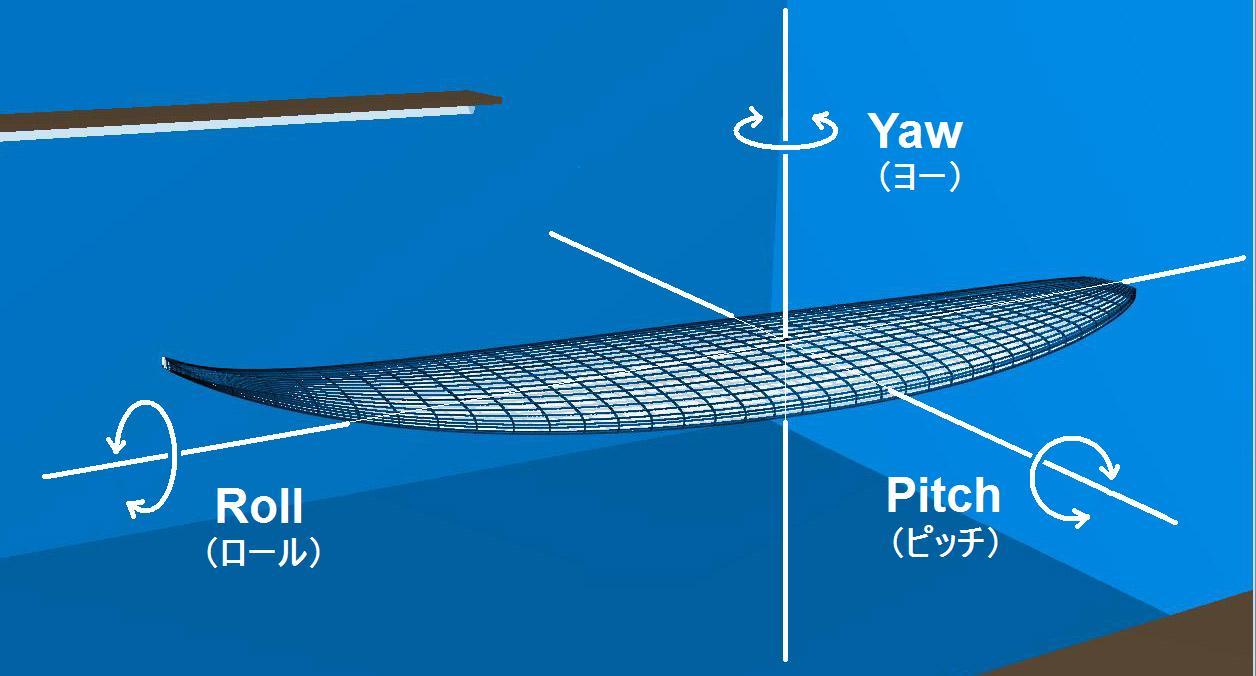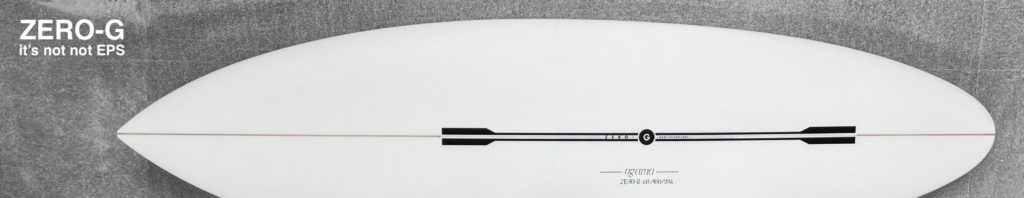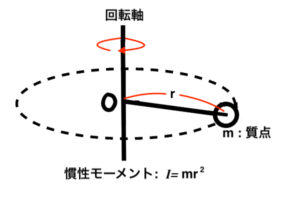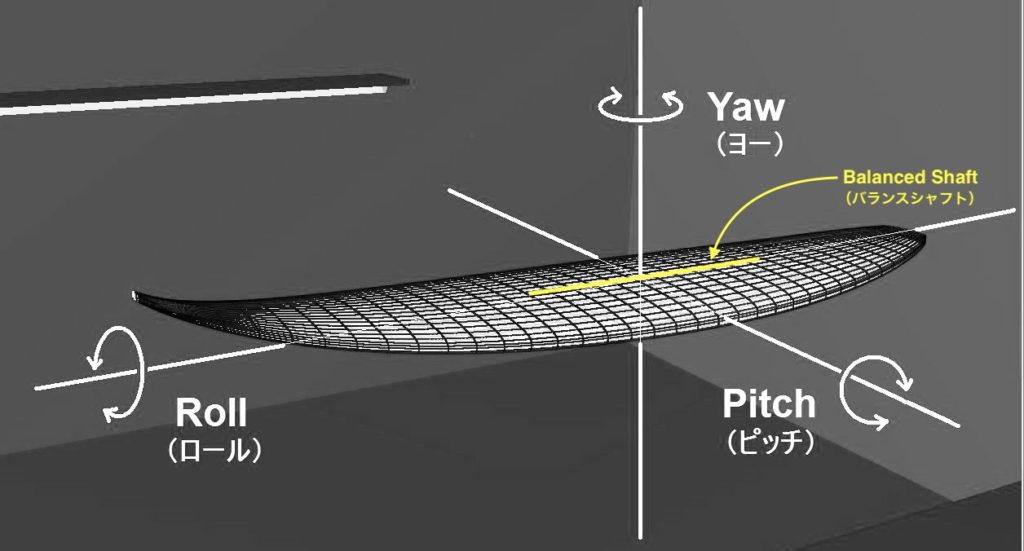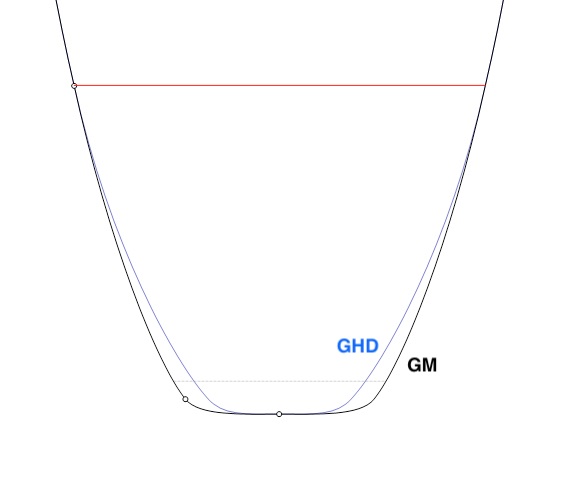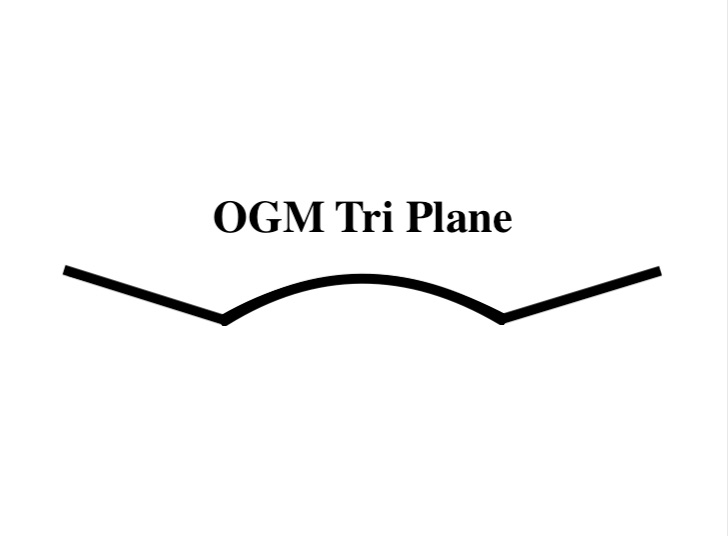
テイクオフを早くするためにはどうすれば良いのか?
最近、パドル力が落ちてきたせいか、いつもこんなことを考えています。
ボードを大きくすれば解決するのは簡単ですが、それでは操作性が重くなってしまい、嫌だと感じるサーファーも多いのではないでしょうか。
テイクオフが早く、立ち上がった後も軽快で自由で、さらに速いサーフボード。
そんな夢のようなサーフボードを作りたいと常に思っています。
毎日のトレーニングで少しは改善できるかもしれませんが、私はシェイパーですので、サーフボードの改良のみで解決したいと考えています。😁
まず、パドルの速度を上げるためには、ボードに十分なボリューム(浮力)が必要です。
しかし、操作性を保ちながら回転性を良くするためには、ボードの長さを抑える必要があります。
結果として、短くて幅の広いサーフボードが理想となるのではないでしょうか?
ボードの幅を広げることには多くの利点があります。
テイクオフが早くなるだけでなく、安定性が増し、小波での加速性能が向上し、速度が低下してもライディングを続けやすくなるなどです。
しかし、幅広のボードにはデメリットもあります。
速度が上がるにつれてレールの切り返しが重くなり、縦の動きが難しくなるため、ライディングが2次元的でフラットなものになりがちです。
これを解消するために、幅広のボードではコンケーブの代わりに主にVボトムが採用されます。
Vボトムは、ボトムを流れる水を左右に逃す性質があるため、ロール方向のモーメントを軽減し、ボードを傾けやすくする効果があります。
このため、ロングボードやミッドレングス、レトロフィッシュなど、大きめのボードにVボトムが多く使われているのです。
しかし、Vボトムは揚力を生みにくく、ボードが走り出しても水に浸かっている体積があまり減らないため、速度が上がりにくく、加速や反応が鈍く感じられることがあります。
特に、最近のサーファーはコンケーブの持つ軽快な走りに慣れているため、Vボトムのボードを「遅くてまったりしている」と感じることが多いようです。

トライプレーンの利点
トライプレーンは、中央にコンケーブを施し、その両側にフラットなパネルを配置した3つの面(トライプレーン)で構成されています。
このボトム形状の理論は、Vボトムの頂点付近をコンケーブで置き換えることでスピード性を確保し、左右のフラットパネルでレールの切り返しを軽くするというものです。
実は、このトライプレーンのアイデアは新しいものではありません。
30年ほど前に、操作性の優れたコンケーブデザインとしてトリプルやクアトロなどのマルチコンケーブが流行しましたが、時代の流れと共に終息しました。
このときのコンケーブ配置が、現在のトライプレーンの原型となっています。
その後、サーフボードの主流はフルコンケーブデザインへと移行し、より小さく効率的なボードが求められるようになりました。
しかし、あれから30年が経ち、当時のサーファーたちも年を重ね、体重が増え、大きめのボードが必要になってきています。
このような状況では、トライプレーンはボードを大きくしても動きが重くならず、スピードも遅くならないため、非常に有効なコンセプトです。
トライプレーンは、軽快で加速性が高く、レールの切り返しが軽いので、サーフボードの大きさを感じさせません。
さらに、シェイプ時の自由度が高く、さまざまな乗り味を作り出すことが可能です。
OGMでは、このデザインが幅広の小波用ボードやミッドレングス、SUPなど、十分な浮力を必要とするボードに対して非常に有効だと考えています。